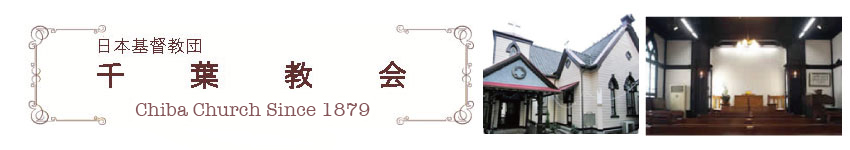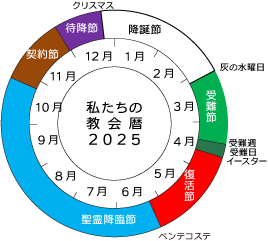教会の暦から
復活祭(イースター)へ
4月18日の受難日(十字架で死なれた日)の2日後(3日目)の4月20日は、復活節、イースターです。主イエスが死者から復活し,その弟子たちと共に過ごされて,「死は終わりではない」ことを示してくださいました。
死者からの復活は,キリスト教を信じようとするときの一つのハードルになるかもしれません。しかし,生前のイエスを知っている弟子たちが「確かにイエス先生は生きておられる」という多くの体験をしたことは,確かなのだと思います。そして弟子たちは,その体験を通じて,自分たちにも復活の希望が与えられたと感じたのです。イエスの復活を信じることができず,イエスさまの傷に自分の指を入れてみなければ信じない,と言っていた弟子に,復活のイエスが現れて,証拠を見せてくれた,という記事が聖書にあります(ヨハネによる福音書20章24節以下十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで、ほかの弟子たちが、「わたしたちは主を見た」と言うと、トマスは言った。「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない。」さて八日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。それから、トマスに言われた。「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」トマスは答えて、「わたしの主、わたしの神よ」と言った。イエスはトマスに言われた。「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである。」)。
私たちにも,イエスさまが一緒にいて,助けてくださっていると感じることがあります。これを,イエスが生きて働いておられる「証拠」と感じることができたとき,イエスに従って生きていこうと思い,自分にとっても「死は終わりではない」と信じることができます。「復活」が医学的にどのような出来事であるかの説明は,人間の科学が完全でない以上,できていませんし,できないのかもしれません。しかし,イエスさまに助けられたという体験は,神の愛を信じるための確かな証拠と感じられることがあるのです。
イエスが,「律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」と言われると,彼は答えた。「『心を尽くし,精神を尽くし,力を尽くし,思いを尽くして,あなたの神である主を愛しなさい,また,隣人を自分のように愛しなさい』とあります。」
イエスは言われた。「正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。」
(ルカによる福音書10章25~28節)」が最も重要だと語っておられます。
「隣人を愛する」とは,「自分に余裕があるから,隣人に分けてあげる」ということではありません。それでは「自分のように」愛したとはいえないからです。自分の持ち分が減る覚悟で,隣の人に助け・与える。分け合うことです。これは,キリスト教での「罪」という言葉が,神様から離れて人間の独善で行動すること,自分中心に欲ばること,であることからすると,罪の正反対であることがわかります。
自分の欲のために他人を責め・殺すこと――ハラスメント,権力闘争,戦争は,このような「罪」の典型です。地球温暖化など,地球規模で人間が住みづらくなっていますが,その中でも,お互いが「身を削って」でも「分け合って」,平和を創り出すことができるよう,祈りましょう。
〔一部に,ホームページ担当の一信徒の考えを書かせていただきました。〕